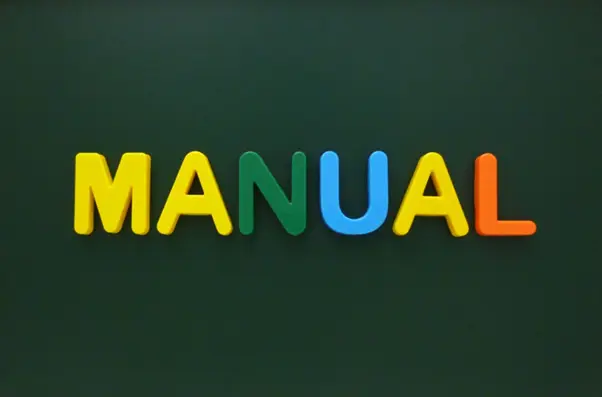
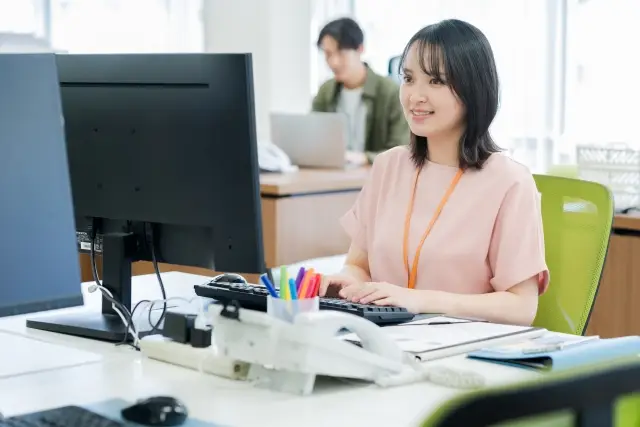
簡潔な表現を使う
「残業時間を減らすため、事務作業を効率化させたい」
「従業員には、売上や利益に直結するコア業務に集中してほしい」
このような悩みを抱えている企業は、多いのではないでしょうか。
本記事では、個人・組織それぞれで取り組める、事務作業を効率化するための手法をご紹介します。
業務効率化の進め方についても解説するので、ぜひ参考にしてください。
事務作業とは、組織や企業の運営に必要な書類の作成や請求書の発行、メール対応など、机上で行われる業務のことです。
以下は、部署ごとの事務の業務例です。
部署名 | 業務例 |
総務部 | 社内規定の更新、備品の発注、契約書の管理など |
人事部 | 入社・退社手続き、採用面接日程調整、勤怠管理など |
経理部 | 請求書・領収書の処理、経費精算処理など |
営業部 | 顧客データ入力、見積書作成、営業報告書作成など |
マーケティング部 | アンケート結果の集計・分析、競合他社情報の収集・整理など |
カスタマーサービス部 | コールログの品質チェック、FAQ資料の作成・更新など |
その他、メールや電話などの業務連絡も事務作業に含まれます。
すべての部署で日常的に多くの事務作業が発生しているため、全社的に事務作業の業務効率化を進めることは、組織の生産性向上につながります。
本章では、事務作業の業務効率化のメリットを解説します。
コア業務に集中できる
コスト削減につながる
従業員のモチベーションアップ
定型的な事務作業が効率化されることで、直接的に企業の利益や売上を生み出すコア業務に集中することができます。
データ入力や文書管理、伝票処理などの作業は、組織を運営する上で必要な業務です。しかし、これらは企業の新しい価値創造につながるコア業務ではありません。事務作業を効率化するための手法を導入し、工程を最適化することで、作業にかかる労力を削減することができます。効率化によって得られた時間やリソースは、製品開発やマーケティング戦略の立案といった、企業の競争力を高める業務に集中させることが可能です。
事務作業はすべての部署で日常的に行われる業務です。作業量や種類が多いと、従業員の業務時間を圧迫し、残業の増加を招く要因にもなります。
そのため、事務作業の効率化を図ることで、業務時間や残業時間を削減することが可能です。全社的に残業を減らすことができれば、大幅な人件費削減につながります。
さらに、業務効率化により作業ミスや漏れが減少すれば、業務の手戻りが少なくなり、その対応にかかる時間や人的コストの削減も期待できます。
事務の業務効率化により作業時間を短縮することで、従業員のモチベーションアップにつながります。
残業時間が削減されると、従業員はライフワークバランスを保ちやすくなります。余暇で休息や気分転換が十分にできることによって、業務への集中力が向上するでしょう。
また、家庭で過ごす時間が増えるため、子育てや介護を理由とした離職を防ぐことにつながります。
その他にも、作業時間が短縮されることで、新たなスキル獲得の時間の確保が可能です。そこから、新たな業務への挑戦や昇進の機会へとつながり、従業員のモチベーションアップが期待できます。
本章では、事務作業の効率化の進め方を解説します。
現状を把握する
業務の問題点を洗い出す
目標を設定する
手法を検討・実施する
評価・分析する
事務作業の効率化を進めるためには、現状を把握することが重要です。現状の把握が不十分な場合、根本的な問題を見逃してしまう危険性があります。
現状を把握するためには、以下のような手法が有効です。
業務フローチャートの作成 | ・業務の流れを可視化し、全体像を把握する ・不要な手順や重複作業を特定する ・作業に携わる人員を把握する |
作業時間の測定 | ・各作業にかかる時間を計測・記録する ・時間ごとのアウトプット量を把握する |
担当者へのヒアリング | ・担当者がどのように業務を進めているかを確認する ・現場の課題や改善アイデアを収集する |
ITシステムの利用状況の確認 | ・使用しているITシステムの活用度を把握する ・未使用の機能がないかを確認する |
これらの手法を組み合わせることで、より包括的に現状把握を進めることができます。
現状把握で得られた情報をもとに、現在の業務に「ムダ・ムラ・ムリ」がないかを確認しましょう。
「ムダ・ムラ・ムリ」とは、事務作業の効率化を実現するために着眼すべき要素を指す言葉です。これらの3つを排除することで、生産性を高めることができます。
<ムダ>
ムダとは、価値を生まない作業やリソースの浪費を意味します。
事務作業におけるムダとは、次のような種類があります。
ムダの種類 | 例 |
作りすぎのムダ | ・不要な情報を含めた資料を作成する |
待ち時間のムダ | ・上司に承認を得るために作業を中断する ・他部署からデータが届かず、待機する |
移動のムダ | ・提出書類は関連部署に手渡ししている ・印刷のたびに、プリンターのある場所まで移動する |
加工のムダ | ・必要以上に資料を装飾する ・既存のフォーマットを流用せず、新たに資料を作成する |
手戻りのムダ | ・誤字脱字により書類を修正する ・上司からの追加指示で、報告書を書き直す |
<ムラ>
ムラとは、不均一な作業ペースや不安定な作業内容を指します。ムラがあると業務を円滑に進めることができません。
以下の点に着目することで、業務のムラを見つけることができます。
ムラの種類 | 例 |
作業ペースのムラ | ・月初や月末に業務が集中する ・納期が迫ると急いで作業をするが、通常時は作業のペースが落ちている |
品質のムラ | ・同じ作業でも、従業員によって品質がばらついている ・品質基準が設定されていない |
人員のムラ | ・特定の従業員に業務が集中している ・チーム間で負荷が偏っている |
<ムリ>
ムリとは、従業員が有している能力や体力以上の業務を行うことです。ムリがある業務は、品質低下やミスの発生につながります。
以下の点に注意して、業務のムリを洗い出しましょう。
ムリの種類 | 例 |
業務量のムリ | ・少ない人数で、多くの仕事をこなさなければならない ・短時間に、複数の作業をしなければならない |
スキルのムリ | ・従業員のトレーニング不足で作業が遅れている ・手順が複雑すぎて、従業員が覚えることができない |
時間のムリ | ・十分な準備時間がない状態で、無理な納期が設定されている ・過去の実績を考慮せず、楽観的な納期が設定されている |
現状把握・問題点の洗い出しをもとに、明確な改善目標を設定します。目標設定は、具体的で測定可能なものにすることが重要です。このような目標設定をする際に活用できるフレームワークが、「SMARTの法則」です。
SMARTの法則とは、次の単語の頭文字を取った言葉で、目標設定のための5つの要素を指します。
Specific(具体的に) | 「誰が」「何を」「どのように」「いつまでに」などを具体的にする |
Measurable(測定可能な) | 達成度が測定可能な数値目標を設定する |
Achievable(達成可能な) | 現状を考慮し、達成可能な目標にする |
Related(経営目標に関連がある) | チームや組織の方針に合致した目標にする |
Time-bound(期限がある) | 明確な期限を設定し、一定期間内に達成できる目標にする |
SMARTの法則を目標設定に取り入れることで、明確で効果的な目標を立てることができ、事務作業の効率化の進捗を管理しやすくなります。
目標を設定した後に、事務作業の効率化のための具体的な手法を選定し、実施します。
導入する手法を検討する際は、従業員のスキルや業務の特性、組織文化などを考慮することが重要です。
業務効率化のために選んだ手法が適切に運用されていない場合、業務上の混乱を招き、従業員の負荷が増えてしまう危険性があります。実際に業務を担当する従業員の意見を取り入れながら、事務作業の効率化のための手法を検討すると、導入が円滑に進むでしょう。
また、手法を本格的に導入する前に、試験的に実施することも重要なポイントです。試験的に実施することで、事前に問題点を発見し、改善することができます。この工程を経ることで、業務効率化の精度を高めることが可能です。
実施した業務効率化の取り組みは、必ず評価・分析するようにしましょう。このステップでは、設定した目標に対する達成度と成果を検証します。また、事務作業の効率化に取り組む中で発見された新たな問題点や課題を分析し、対策を検討します。
この評価・分析は従業員にフィードバックし、次の取り組みに活かしましょう。
事務作業の効率化は、企業全体の生産性向上に直結します。その実現には、個人と組織の双方による積極的な取り組みが必要です。
個人における事務作業の効率化では、各自が自分の業務への取り組み方を見直し、自己管理や改善を行うことです。個人が効率的に働くことで、チームや組織全体の業務にも良い影響を与えます。
組織での業務効率化は、個人の取り組みを支援しながら、組織で統一された方針にしたがって改善策を導入していくことです。組織での取り組みは、個々の業務効率を高めるだけでなく、全体的な業務フローの改善にも寄与します。
このように、個人が主体的に取り組むとともに、組織が適切な環境や体制を整えることで、より大きな効果が期待できます。
次章以降では、個人レベル・組織レベルで取り組める事務の業務効率化の手法をそれぞれご紹介します。
本章では、個人で取り組める事務作業の効率化の手法を4つご紹介します。
業務の優先順位をつける
データや書類を整理整頓する
資料・メールのテンプレートを作成する
報告・連絡の要点を明確にする
1つの作業に集中することで、効率良く業務を進めることができます。そのために、業務を開始する前に、優先順位を明確にしてから取り掛かるようにしましょう。
効果的な優先順位の付け方として、アイゼンハワーのマトリクスというものがあります。業務を緊急性と重要性を軸に、4つに分類します。この手法により、集中すべき業務を明確にすることが可能です。
分類 | 対応 | 例 |
1.緊急、かつ重要 | 今すぐ実行 | 提出期限が迫った資料の作成 |
2.緊急ではないが重要 | 計画的に実行 | 業務マニュアルの作成 |
3.緊急だが重要ではない | 別の担当者に任せる | 予定外の問い合わせ対応 |
4.緊急でも重要でもない | 削除/後回し | 必要以上に凝った資料の作り込み |
データや紙の書類を整理し、必要な情報にすぐアクセスできるようにすることで、業務時間の短縮が可能です。平均的なビジネスパーソンが探し物をする時間は、年間150時間ともいわれています。日々の中では、些細に感じられる探し物の時間ですが、実は大きな時間の浪費になっています。
以下のような手法で、データや書類を整理することができます。
<データ整理のコツ>
ファイル名のルールを統一する
プロジェクト単位でフォルダを作成する
フォルダの階層は深くしすぎない
<書類整理のコツ>
タグやラベルを使って分類する
定期的に不要な書類を処分する
現在必要な書類と、保管用の書類を分けて管理する
データや書類の整理整頓は、習慣的に行う必要があります。あらかじめ、スケジュールに整理整頓の時間を設定するようにしましょう。
資料やメールのテンプレートを作成すれば、作業時間の短縮とミスの削減という2点で、事務作業を効率化することができます。
テンプレートを利用することで、基本的に決まった書式に従って資料やメールを作成できるため、作業時間を短縮することが可能です。
メールのテンプレートの場合、顧客への報告文や案内文など、定期的に使用する文書はあらかじめテンプレート化するようにしましょう。
資料の場合、会議の議事録やプロジェクトの報告書、プレゼン資料などのテンプレートを用意しておくと、新たにデザインを整える必要がなく、内容に集中することができます。
また、テンプレートの活用は、ミスの削減にもつながります。新たに文章を作成する場合、情報の抜け漏れや記述ミスが発生しやすくなります。テンプレートを活用すれば、必要な項目や基本的な情報を含めることができるため、これらのミスを防ぐことができるでしょう。
社内外を問わず、報告・連絡をする際は、必ず要点を明確にするようにしましょう。要点が不明瞭である場合、伝達ミスやクレームにつながりかねません。業務を円滑に進めるために、報告・連絡を的確に行うことが重要です。
報告・連絡の要点を明確にするには、次のようなポイントを意識すると良いでしょう。
5W1Hを活用する | 以下の要素を抑えることで、相手が理解しやすい報告ができる。 ・Who(誰が):担当者 ・What(何を):報告の内容 ・When(いつ):期限、スケジュール ・Where(どこで):関連する部署、場所 ・Why(なぜ):理由、目的 ・How(どのように):進め方、方法、手順 |
趣旨や結論を先に伝える | 重要なポイントを最初に伝えることで、相手が内容をすぐに把握でき、後の説明を理解しやすくなる。 |
簡潔な表現を使う | 不要な情報を削り、短い文章で報告することで、要点が明確になる。 |
本章では組織で取り組む、事務作業の効率化の手法を3つ解説します。
業務をマニュアル化する
ITシステムや自動化ツールを導入する
アウトソーシングを活用する
業務をマニュアル化することで、組織全体の効率化や品質向上、人材育成に大きく貢献します。
まず、マニュアル化を進める中で、業務の工程が可視化されるため、非効率な作業を発見することができます。それにより、具体的な改善策の検討へとつなげることが可能です。
また、マニュアルに手順が明記されるため、作業の抜け漏れを防ぎ、一定の品質を保つことができます。
さらに、マニュアルがあれば、担当者の不在時でも、業務を継続することができるため、新人教育や引継ぎが効率的に行えます。
以下は、効果的なマニュアルの作成のポイントです。
視覚的な工夫 | ・業務の目的と成果物を明記する ・図やイラスト、画像を活用する ・重要なポイントをわかりやすく表記する |
検索性の向上 | ・目次や索引を充実させる ・デジタル化する |
メンテナンス | ・定期的な見直しと更新を行う ・バージョンの管理を徹底する |
ITシステムや自動化ツールを導入することで、事務作業の効率化が飛躍的に進みます。これにより、人的ミスを減らし、より付加価値の高いコア業務に集中することができます。
以下は、業務効率化に役立つITシステムや自動化ツールです。
システムの種類 | 特徴 |
RPA(Robotic Process Automation) | 定型的な事務作業を自動化するための、ソフトウェアロボット。日次リポート作成、勤怠管理、顧客データ登録などを自動化することができる。 |
クラウド型のグループウェア | 複数の業務ツールを統合したプラットフォームで、業務の進捗管理やコミュニケーション、文書の共有などが可能。リアルタイムで情報共有ができるため、待ち時間のムダを削減することができる。 |
電子契約システム | 契約書を電子署名を使って締結するシステム。印刷や郵送のコストを削減し、契約の工程を迅速化することができる。 |
会計・経費精算システム | 経理業務に特化したシステムで、煩雑な経費精算や帳簿管理などを自動化することができる。 |
これらのシステムを導入することで、業務の工数を減らし、従業員の負担を軽減することができるでしょう。
アウトソーシングとは、自社の業務の一部を、外部の専門企業に委託することです。
アウトソーシングを活用することで、経理や営業事務など、それぞれの分野に精通したスタッフが業務に対応するため、短時間で高品質なアウトプットが期待できます。社内で時間がかかっていた業務を委託することで、従業員がコア業務に集中できるようになるでしょう。
また、アウトソーシングは業務量に応じて依頼をすることができるため、事務の要員として新規採用する場合と比較して、人件費を抑えることが可能です。アウトソーシングは、事務の業務効率化のための、コストパフォーマンスの良い手法といえます。
「事務作業の効率化はしたいが、導入に手間のかかる手法は避けたい」といった場合は、NTT印刷株式会社が提供するカチアルサポートがおすすめです。
カチアルサポートは、バックオフィス業務の代行サービスであり、経理・営業事務・人事/採用・秘書・クリエイティブなど、さまざまな業務の依頼が可能です。
カチアルサポートでは、窓口専属スタッフが、依頼業務内容を適切にヒアリングします。その後、企業の要望に合わせたスタッフでチーム体制で業務を行うため、導入に手間がかかりません。
また、業務マニュアルの作成も依頼できるため、業務依頼にあたって自社でマニュアルを用意する必要がなく、初めて業務効率化に取り組む企業であっても、負担なく業務を委託することができます。
業務に対応するのは、厳しい採用過程を通過した100%正社員のスタッフです。各分野に精通したスタッフが、高い品質のアウトプットを提供します。
そして、アサインされるスタッフは、サービス提供元拠点に出社して、管理者の監督のもと業務に従事するため、セキュリティ面でも安心です。
さらに、カチアルサポートでは、依頼業務を自由に組み替えることができ、月ごとに依頼する内容を変更することができます。そのため、繁忙の波がある企業にも取り入れやすいサービスです。
費用 | 初回限定エントリープラン 43,000円/月(税込 47,300円) 月内利用時間12時間、契約月数3カ月 スタンダードプラン 118,000円/月(税込 129,800円) 月内利用時間30時間、契約月数12カ月 |
業務範囲 | 経理、営業事務、人事/採用、秘書、クリエイティブなどに幅広く対応 |
特徴 | ・業務の切り出しサポートや、マニュアル作成も依頼でき、初めてのアウトソーシング活用に適している ・100%正社員の厳選されたスタッフがサービス提供を行うため、業務のアウトプット品質も安心 ・スタッフがサービス提供元拠点に出社して業務を行うため、セキュリティの心配も不要 |
本記事では、事務作業の効率化のメリットや進め方、効率化の手法などについて解説しました。
記事のまとめは、以下の通りです。
事務作業の効率化のメリットは、コスト削減や従業員のモチベーションアップ、コア業務へ集中ができること
業務効率化を進めるためには、個人と組織の双方が積極的に取り組む必要がある
個人で取り組める業務効率化には、業務の優先順位付けやデータ・書類の整理整頓、テンプレートの利用などがある
組織で取り組む業務効率化には、業務のマニュアル化やITシステムの導入、アウトソーシングの活用などがある
人手不足が深刻化する中で、従業員が働きやすい環境を整備することは、企業にとっても大きな課題です。煩雑な事務作業が効率化することで、従業員の負担を減らすことができます。
また、コア業務に集中できることで、企業の業績アップにも期待できます。
企業と従業員の生産性向上のために、積極的に事務作業の効率化に取り組みましょう。